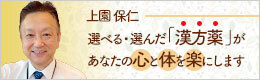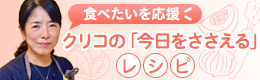「当事者意識を持とう」。「自分事として考えよう」。私たちが働く日常において、こうした言葉を耳にすることは少なくありません。企業や組織に貢献する意味のみならず、私たちが働きがいを感じる上で、主体性や当事者意識を持つことは確かに大切なことです。
今回は「当事者」という言葉について、考えてみたいと思います。
「私たち」だからこそわかること
海の向こうでの昨今の動きは非常に気になるものの、この十数年、日本におけるダイバーシティの取組みは着実に広がってきました。女性活躍推進に始まり、様々な事情に配慮した柔軟な働き方もできるようになってきています。
その中で忘れてはならないのは、第23回 (改めて考える「対話」の重要性)でも紹介した「私たちのことを私たち抜きで決めないで」という言葉だと思います。日本も署名、批准した国連の「障害者権利条約」が作成される際の当事者たちの合言葉は、障害に限らず、病気の治療や育児・介護等の事情を抱える人、さらには企業や組織で働く一人ひとりにも通じるものでしょう。
対話や発信によって当事者の実情や思いを具体的に届ける場の重要性は、決して忘れてはなりません。

このコラムでも何度かお伝えしていますが、私が勤務するサッポロビールには、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars」があります。がんを経験した社員同士のピアサポートを中心に、社内外への発信も行っています。当事者だからこそわかることもある中、一般社員向けに発信することで、認識のギャップを埋めていければと考えています。
ここでいくつかの疑問が浮かびます。当事者とそうでない人の溝は決して埋められないものなのでしょうか。そもそも「当事者」とは誰のことを言っているのでしょうか。
「当事者」になるということ
個人的な話ですが、7月に広島を訪れました。真夏の太陽が照り付ける中、原爆ドームの前にしばし佇み、平和記念公園の中を歩いていくと、静寂の奥から祈りの声が聞えてくるような気がしました。私もその声の一人となるべく、慰霊碑の前で目を閉じ、手を合わせました。
広島や長崎では、被爆者たちが高齢化し、旅立っていく中、被爆者の記憶の継承の観点から、体験を語り継ぐ人たちを含めて「伝承者」と捉える動きが出ているようです。
例えば広島市は、2012年度から被爆体験伝承者等養成事業として、自らの被爆体験等を伝える「被爆体験証言者」、被爆体験証言者の体験や平和への思いを受け継いで伝える「被爆体験伝承者」の養成を開始すると共に、2022年度からは、家族の被爆体験等を受け継いで伝える「家族伝承者」の養成にも取組み始めたとのことです。(※)
私自身の解釈として、こうした取組みは「当事者」を広義の意味で捉えていこうという動きと言えるのではないでしょうか。
何も大きな話だけではありません。様々な事情を抱える人を前にした身近なところで、少しばかりでも想像力を持つこと。問題解決をとかく急ぎがちな日常のモードから一旦立ち止まり、事情を抱える人の思いに寄り添うべく受容・共感モードに切り替えること。
その小さな積み重ねによって、各所で「当事者」の輪が少しずつ広がっていくことを願ってやみません。

※被爆者の被爆体験や平和への思いを次の世代が語り継いでいく「伝承者」の存在 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/peace80/hibakusha-family-member-legacy-successors.html

サッポロビール株式会社 人事部 プランニング・ディレクター
1964年東京都生まれ。
1987年サッポロビール入社。
2009年に頸部食道がんを発症し、放射線治療で寛解。11年、人事総務部長在任時に再発し、手術で喉頭を全摘。その後、食道発声法を習得。
14年秋より専門職として社内コミュニケーション強化に取組む一方、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars」の立上げ等、治療と仕事の両立支援策を推進。
現在はNPO法人日本がんサバイバーシップネットワークの副代表理事や厚生労働省「がん診療連携拠点病院等の指定検討会」構成員も務めている。
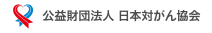


 第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」
第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」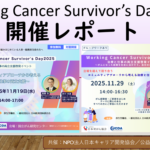 【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」
【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」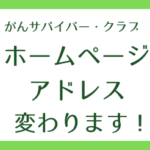 WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ
WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐
クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐