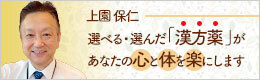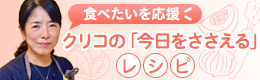本人でなければわからないこと
MDアンダーソンがんセンターが発信しているさまざまな記事の中に、「バーチャルがん支援グループを最大限に活用する方法」と題したものがありました。 https://www.mdanderson.org/cancerwise/how-to-get-the-most-out-of-virtual-cancer-support-groups.h00-159382734.html

MDアンダーソンは、ボランティアの制度がとても充実している病院です。中でも、がんサバイバーの方達によるがん患者さんへのサポート、いわゆるピアサポートは、私の知る限りでも、25年以上前から続いています。
私も家族にがんサバイバーがいます。そしてがんの人をサポートする仕事をしています。それでも、家族も含めて、「がんサバイバーの気持ちを本当の意味で理解できている」と胸を張って言うことはできません。 がんになった本人でなければわからないことがありますよね。
新型コロナウイルスの感染が拡大する以前、MDアンダーソンの院内には、がん患者さんが交流できる場所があり、飲み物や食べ物が置かれ、がん経験者が常駐していました。 ここでは、訪れたがんサバイバーに、同じがん種や似たような経緯のある人をマッチングさせて、電話で話せるなどの仕組みがありました。
しかし、今回の記事の筆者、サラ・ジツィニア(SARAH ZIZINIA)さんによれば、現在は、新型コロナウイルスから守るため、MDアンダーソンのソーシャルワークカウンセラーは、がん支援グループをバーチャルなものに移行しています。
とはいえ、対面と同様に、同じ課題と向き合う人とつながり、気持ちを率直に話し、実践的なアドバイスを受け、がんに対応するスキルを伸ばすことができる場を提供しています。

MDアンダーソンがんセンター。いかつい建物で働く人たちの心は温かい。
聞いているだけでも多くのものを得られる
では、バーチャルがん支援をよりよく受けるためのヒントは何でしょう? MDアンダーソンのお勧めをまとめました。 ①バーチャルがん支援グループに参加するにあたっての準備 ・バーチャルがん支援に集中できるように、快適で静かな場所を見つける。 ・オーディオやビデオの機能をテストして、ヘッドフォンを用意する。 ・カメラをオンにしたり音声をミュートにしたりするなどの操作、バーチャル空間でグループ内を移動する方法など質問や心配事があれば、あらかじめ支援グループのリーダーに聞いておく。
②バーチャルがん支援グループ内での行動について ・新しい人との出会いに心を開く。 ・いくつかのグループミーティングに参加できない時があっても、気にせず、戻ってくる(時間があればいつでも参加できる)。 ・動画を使わなければならないと思わない(電話のほうが快適という人もいる)。 ・どんな局面でも不安や不快感を覚えたときは、グループのファシリテーターに声をかける。 ・グループをよりよくするために、提案やフィードバックは自由に行う(このグループはあなたのためのもの)。 ・自分のことをグループの他者と共有したくない(話したくない)時はしなくていい。ただ聞いていればいい。他の人の経験を聞くことからも、多くのものを得られる。
30近くにも上る支援グループ
実際に、バーチャル支援グループを運営しているソーシャルワークカウンセラーたちは、新しい形式の支援について、どう見ているのでしょう?
メラニー・カヴァゾス(Melanie Cavazos)さんは、取材にこう答えています。
「今までサポートグループに参加するのは地域の患者さんだけでしたが、遠隔地の患者さんが継続して参加できています。地元の患者さんも、(MDアンダーソンのある)ヒューストンの交通渋滞や病院の駐車場などに関する煩わしさが減ります」
また、ソニア・ジュラード(Sonia Jurado)さんはこう語っています。 「多忙なスケジュールにも柔軟に対応できる。患者さんは、別の予定の準備や会議に行く心配をすることもなくなります。都合のよい日時に他のサバイバーとの有意義なつながりを見つけられる素晴らしい機会です」

MDアンダーソンでは、バーチャルがん支援グループが、30近くにも上ります。 一般的ながん患者サポートグループだけでも、曜日や、スペイン語を話す人向けなど6つに分かれています。
ほかに、ケアする人(ケアギバー)、LGBTQIA(性的マイノリティー)、AYA世代(MDアンダーソンでは18歳~39歳)、がんの子どもを持つ親といった“属性”、一般婦人科系、幹細胞移植/血液がん、転移性乳がん、乳房手術・再建といったがんの状況、などに応じて用意されています。 こうしたきめ細かさからも、MDアンダーソンの姿勢が伝わってきます。
https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/patient-support/support-groups.html
私は、特に内面的な人と人との触れ合いに関して、バーチャルというものに抵抗を感じるほうです。ただ、人のぬくもりを直接感じられない寂しさはあるものの、バーチャルな場だからこそ話せることもあるかもしれません。
バーチャルもリアルも、まずは参加してみて居心地のいい場所を見つけていく、という意味では同じだと思います。それは、米国でも日本でも、変わらないでしょう。
いくらか落ち着いてきたとはいえ、まだコロナの影響が大きい時期、身体的そして精神的につらいことも多い時期に、どんな方法であれ、楽しくて心が休まる場所が見つかることを願います。

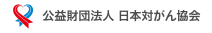


 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内
「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 長期休みの不安をどう解消する?
長期休みの不安をどう解消する? 第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」
第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」