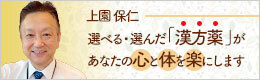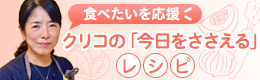父の急死で39歳で僧に
1946年、栃木県益子町にある真言宗の西明寺に長男として生まれる。東京慈恵会医科大学に進み、卒業後は国立がんセンターで内科医になる。 1982年6月、突然、住職の父が心筋梗塞で亡くなり、翌年3月がんセンターを退職。大正大学仏教学部で僧侶の勉強をして、1984年6月、39歳で西明寺の住職を継ぐ。 1990年、寺の中に医療施設「普門院診療所」を作った。西明寺は奈良時代に行基が開いたとされ、当時12あった坊から命名した。 2014年10月上旬、その普門院診療所で超音波検査を受けたところ、膵臓とその近くに腫瘍が見つかる。栃木県立がんセンターで検査を受け、ステージⅣbの膵臓がんと診断される。 10月末に膵頭十二指腸切除の手術を受け、12月末に退院。術後補助療法として抗がん剤TS-1(ティーエスワン)を6カ月間使用。 2015年6月、CT検査で肝臓への転移が見つかる。アブラキサンとジェムザールの2種類の抗がん剤治療を受ける。 同年12月の検査で肝臓への転移が大きくなっていることが判明。日本では2013年に承認された「フォルフィリノックス療法」を試みる。3種類の抗がん剤を含む薬剤(ロイコボリン、イリノテカン、エルプラット)を4時間くらいかけて点滴し、その後、5-FU(フルオロウラシル)を46時間かけて注入する。これを2週間に1度行う。 2016年2月半ばのCT検査では、がんは縮小していた。

民間療法を否定
著者は医師の立場から「医学は科学」と定義づける。「きちんと検証された知識に基づいて、適切な結果を求める世界です。徹底的にエビデンスを重視します」とし、勝手な解釈を介在させ「科学の土俵にのることを怠っている」民間療法を否定する。 民間療法に騙されないためのポイントを5つ挙げている。 ①その治療者は、きちんとした資格を持っているか 療法を行う者が医師免許など正式な資格を持っているのか確認すること。 ②メリットだけでなく、デメリットもはっきりと提示されているか その療法の効果だけでなく、副作用などの弊害が明らかにされているかも重要。 ③ほかの治療法を否定し、それだけをやるように勧めないか 現代医学で認められている標準治療を否定して、「これをやればがんが消える」といった勧め方は信じてはダメ。 ④過剰なお金がかかりすぎないか 保険が効かず、経済的に過度な負担を強いるものは疑うべき。 ⑤不確かな情報を鵜呑みにしていないか 有名人が紹介したからと簡単に信じてはいけない。 また、「漢方薬は自然由来のものだから副作用がない」と思い込んでいる人にも、医師として警鐘を鳴らす。 「漢方薬は効きます。効くから危ないのです。効くということは必ず副作用もあるということです」 もし「この漢方薬は副作用がありません」といわれたら、「それは効果もないと思っていいのです」といい切る。
医療現場に宗教者を
一方で、宗教者の立場からは、医療現場には患者に寄り添う専門家が必要と訴える。 死に関わる苦しみを「スピリチュアルペイン」といい、日本語では「いのちの苦」と呼ぶ。 「身体や心の痛み・苦しみは薬で抑えることができますが、『いのちの苦』は医学という科学では癒やすことができません」という。世界的に見て、それができるのは宗教者や哲学者であると。 キリスト教文化圏のみならず医学の進んだ国では、病院に宗教者、聖職者がいて、患者に寄り添っている。ところが、日本の医療現場には、いのちの苦を緩和する「いのちのケア」を行うプロが、ほぼ皆無と嘆く。 また、医師や看護師がいのちのケアをするのは勘違いであるとも指摘する。患者の語りを傾聴する中で、「その人がいったい何を求めているのかを見抜いて、それに応じたことを話せる」ためには、人文学という「非科学の分野」の知識が必要であると説く。 その知識を持った人こそ、絶望の淵に沈んでいる人の心の持ちようを変えることができ、その人の人生の物語を完成させる手伝いができる。そんないのちのケアの専門家が、緩和ケアや看護ケアのチームに必要だと叫ぶ。
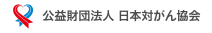



 第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」
第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」 長期休みの不安をどう解消する?
長期休みの不安をどう解消する? 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」