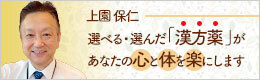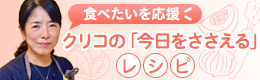日本のがんを取りまく問題に何らかの形でかかわりたいと考える方が、がんに関する知識を学び、ご自身の次のアクションに繋がるヒントを見つけ活力を得られる場を目指したこのセミナーには、がん患者支援活動に理解のある専門家、医師、がんサバイバー、行政担当者が講師として登壇。
約40名の受講生は、日本のがんに関する現状への認識を深め、がんになっても‟希望と共に生きる”ことのできる社会の実現に向けての活動を一緒に考えていきました。
開会の挨拶

セミナー冒頭、日本対がん協会の垣添忠生会長は「アドボケ―ターには、権利の表明のできない人に対しての代弁者あるいは擁護者といった意味がある。本日は朝から大変有意義な計画がされていますので、どうぞ皆さま今日一日を勉強され かつ、楽しんでいただければ嬉しく思います」と開会の挨拶を述べました。
午前の部 ~正しい情報を必要とする方へと届けるために~

受講者はがんに関する正しい情報についての各種動画を事前に視聴しており、セミナー冒頭では北里大学医学部附属新世紀医療開発センター教授の佐々木治一郎先生がまとめ役となり、動画の振り返りや質問に回答しました。佐々木先生は「がんに関する情報はインターネットで得ることが多いと思います。検索するときに『これは正しい情報かな?』という疑いの姿勢から入って、その真偽がわからない時にはガイドラインや法的なもの、学会が出している情報を参照して、自分なりに判断することも必要です」と述べました。

その後「緩和ケアと支持医療のこれまでとこれから」と題し、帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科教授の渡邊清高先生が講演しました。医療技術が進み生存率は向上し、併存疾患や合併症、生活の質(QOL)の維持などの課題もある中で「以前は患者が受け身だったかもしれないが、今は治療もケアも選択肢は多くあります。治療を優先する考え方もあれば、生活を重視する考え方もある。どれが正解ではなく、選択肢・価値観が多様な中で、話し合ってこれからのことを考えていく『話し合う医療』がこれからは大切」と述べ、緩和ケアや支持医療に関する情報を必要としている人に届ける重要性を説明しました。

日本対がん協会 相談支援室の北見知美マネジャー(社会福祉士)は「患者支援のさまざまな資源~がん相談窓口の活用について~」と題し、相談事例を交え、行政の支援制度や医療機関の相談窓口といった社会資源の活用、情報収集の方法を紹介しました。「必要な人へ情報をつなげることが大切。新たな社会資源が必要と思えば声を挙げて作り出し、『その情報を届ける』というところまで、視野に入れていただくと良いと思います」と呼びかけました。

ランチョンセッション「わたしたちにできること」

昼食時にはランチセッションとして、平塚共済病院ピアサポーターの吉田久美さん、乳がん患者支援団体メンタル・スパ代表の大友明子さんが「わたしたちにできること」とのテーマで、ご自身の経験を交えながら支援活動に至る経緯や志をお話しいただきました。

吉田さんは「ピアサポートという活動を起点にいくつもの点が重なり線となり今の自分がある」、「足りないことを感じた時、当事者が声を上げて仕組みを変えていくことが大切だと感じます」と意見を述べ、大友さんは「自分の活動ややりたいと思っていることが『誰のために?』『何のために?』と、常に自問自答することも大切」、「目的がだんだんブレてしまったり違う方向に向かってしまうことがないように、時には問いを立てることも重要」と、これからのアドボケ―ターへメッセージを送りました。
午後の部 ~共に創る社会~

午後の部1講演目は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の勝井恵子さんが「医療研究開発における患者・市民参画(PPI):AMEDにおける『社会共創』推進に向けて」と題し講演。「医療研究では患者さんや市民の皆さんの持つ『経験値』が欠かせない。研究者が気づきにくい課題や視点を教えてくれて、多様な視点や価値観を研究開発に取り入れようとしてくれている」と協力を求めました。

また、国の第3期がん対策推進基本計画の策定に携わり、現在は岐阜県健康福祉部長の丹藤昌治さん、患者代表として国のがん対策推進協議会に長く関わっている一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長の天野慎介さんより、「日本のがん対策とアドボカシー~がん対策を知り、私たちができるがん対策を考える~」とのテーマで、それぞれの闘病経験を交えながら「がんとの共生」についてお話しいただきました。

丹藤さんは「日本のがん対策3本の柱のうち、3本目の「共生社会の構築」が圧倒的に難しいと感じる」という点について、「3本目の柱はナラティブからのアプローチがとても大切」と述べました。天野さんは「医療がこうなって欲しい、こんなサポートが欲しいと思っても、患者や家族はなかなか声を上げることができない。それらひとつでも声を上げて実現していくことが、『がんアドボケータ―』と呼ばれる人たちに期待されていること。社会全体でがんを取り巻く問題を考える時に、アドボケーターの方々が活躍すべきことはたくさんあると思います」と述べ、「是非たすきをつないでほしい」と参加者に語り掛けました。
最後に「わたしたちができること」をテーマにワークショップを行いました。一般社団法人食道がんサバイバーズシェアリングスのメンバーが進行役を務め、受講者それぞれの夢や取り組みたい活動をもとに、活動の対象とする架空の人物像の特徴などを書き出し、誰のために何をするのかを、より具体的に考え意見交換を進めました。

受講者からは、経済的な病に対する相談窓口、地域情報を紹介するコミュニティー、がん患者遺族のグリーフケア、患者と医療者の仲介など、自身の経験や得意分野を生かした課題解決のための様々な活動が語られました。

セミナーの最後には、佐々木治一郎先生から受講者へ「自分自身を大切にすることも大切。自分の限界を知るところから活動は始まりますので、是非気をつけてがんばってください」というメッセージが送られました。

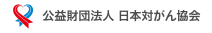


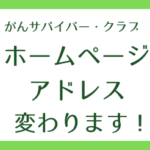 WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ
WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐
クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐 登壇者募集のお知らせ(募集締切:2/16)
登壇者募集のお知らせ(募集締切:2/16) 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内
「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内