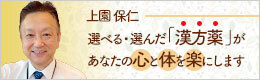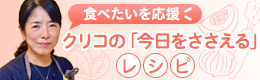日本対がん協会会長の垣添忠生の「全国縦断 がんサバイバー支援ウォーク」は7月23日、札幌市の北海道がんセンターにゴールした。96日間、約3500キロ。歩行距離も約2500キロに及んだ。大雪の九州からのスタート。スマホの故障、体調悪化などを乗り越えて成功できたのは、多くの方のご支援の賜物です。8月4日、感謝の気持ちを込めて、東京・有楽町の朝日スクエアで報告会を開きました。
(文・日本対がん協会・中村智志)
 報告会では、アウトドアの雰囲気が演出された。
会場の正面奥には、キャンプ用の大きなテントが張られていた。
約130人の来場者が拍手で迎える中、月桂樹の冠をかぶった垣添忠生が登場し、リングに上がるボクサーのように客席の合間を進んだ。正面に到着した垣添に、秘書の森田幸子から花束が贈呈された。垣添が達成宣言をした。
「全国縦断がんサバイバー支援ウォーク3500キロ、無事完遂しました。みなさん、ありがとうございます!」
照明が落ちて、前方スクリーンに青森県を歩いていた際の映像が流れる。インクスの中村明夫さん、市谷雅裕さんが撮影してくれたもので、ドローンによる上空からの撮影まで入っている。会場が、一気にウォークの世界に浸っていく。
続いて、中釜斉・国立がん研究センター理事長が挨拶に立った。
「今は、がんとの共生が大きな課題になっています。患者さんを支える、人と人をつなぐ、までは思いつきます。しかしその先、『よし、32の全がん協加盟病院を結ぶために歩こう』と思いつき、実際に行動に移されるというのは驚くべきことです。毎日20キロ、30キロ歩いて、訪れる土地で丁寧な対話を繰り返す。その積み重ねが、サバイバー、医療者、社会そのものにつながっていく。2日ほど前に、(96日分の)一言ブログを通して読み直しましたが、思いが鮮明に表れています。また、垣添先生の一見では想像できない教養や感性の豊かさを感じます」
最後の言葉で、会場がドッと笑った。
報告会では、アウトドアの雰囲気が演出された。
会場の正面奥には、キャンプ用の大きなテントが張られていた。
約130人の来場者が拍手で迎える中、月桂樹の冠をかぶった垣添忠生が登場し、リングに上がるボクサーのように客席の合間を進んだ。正面に到着した垣添に、秘書の森田幸子から花束が贈呈された。垣添が達成宣言をした。
「全国縦断がんサバイバー支援ウォーク3500キロ、無事完遂しました。みなさん、ありがとうございます!」
照明が落ちて、前方スクリーンに青森県を歩いていた際の映像が流れる。インクスの中村明夫さん、市谷雅裕さんが撮影してくれたもので、ドローンによる上空からの撮影まで入っている。会場が、一気にウォークの世界に浸っていく。
続いて、中釜斉・国立がん研究センター理事長が挨拶に立った。
「今は、がんとの共生が大きな課題になっています。患者さんを支える、人と人をつなぐ、までは思いつきます。しかしその先、『よし、32の全がん協加盟病院を結ぶために歩こう』と思いつき、実際に行動に移されるというのは驚くべきことです。毎日20キロ、30キロ歩いて、訪れる土地で丁寧な対話を繰り返す。その積み重ねが、サバイバー、医療者、社会そのものにつながっていく。2日ほど前に、(96日分の)一言ブログを通して読み直しましたが、思いが鮮明に表れています。また、垣添先生の一見では想像できない教養や感性の豊かさを感じます」
最後の言葉で、会場がドッと笑った。
 挨拶をする中釜斉・国立がん研究センター理事長。垣添とは30年以上の付き合い。
挨拶をする中釜斉・国立がん研究センター理事長。垣添とは30年以上の付き合い。
ジェラール・フィリップのはずが……
ここで垣添が、スライドを見せながらウォークの報告をした。 「歩いている写真を見ると、首が前に出て、がに股ですね。昔、ジェラール・フィリップという俳優がいました。映画『赤と黒』(1954年)でらせん状の階段を、白いシャツと黒いパンツをはいてササーッと降りてくる姿がなんと美しいかと思って、そのイメージで歩いていたのですが、実際は全然違いました」 後で垣添いわく。「キルケゴールも言っている。『可能性であったものが現実になることによって、可能性であったとき以上の必然性を獲得するか?』と」。 スライドでは、さまざまな写真が写し出された。スタート時の雪の福岡市。 「大寒波で、ものすごい雪なんです。間違えて北海道からスタートしたかと思いました」 愛媛県と広島県を結ぶ、瀬戸内しまなみ海道の立派な橋。 「人間はこんなに見事な建造物を造る力がありながら、一方で、がんという病気への理解が不十分で患者さんや家族が疎外感や孤立に苦しむのは許されない、と思いながら歩いていました」 肝心の薄造りが写っていないカワハギ。
肝心の薄造りが写っていないカワハギ。新しいことは、1人から始める
垣添は2007年の大みそかに自宅で妻を看取った経験から、自分はひとりで家で逝きたいと考えている。「そのためには、よほど元気でいないとダメです。矛盾した話ですが」と言うと、会場がまた湧いた。 毎朝、絨毯にバスタオルを敷いて、腕立て伏せ150、腹筋500、背筋100、スクワット100、つま先立ち100、各種ストレッチ1時間と鍛えている。出張先でも欠かさない。 ウォークのあちこちで話しているネタだが、今回も驚嘆の声が漏れた。 週に2回稽古している居合道は四段。三段になってから本身(本物の刀)を使っている。緊張感で腕が上がるという。四国八十八ケ所巡りもした。年に3、4回は山登りをしている。こうした経験があるからこそ、ウォークを完遂できたという。 「新しいことを始めるときには、1人から始める。趣旨を理解してもらい支援の輪が広がると、そのおかげで、何事かを達成できる。そう考えています」 1回のウォークで体重は3~5キロ減った。新潟ではスマホが雨に濡れて故障した。写真が撮れなくなったときに、助けてくれたのが、新潟県小千谷市でパソコンショップを経営する平澤智さんだった。新しいスマホが届くまでの間、平澤さんがデジカメを貸してくれたおかげで、ウォークのインスタや一言ブログは中断なく更新できた。 会場には、平澤さんが見えていた。司会者に促されて前方に立つと、 「秘書の森田(幸子)さんからデジカメがほしいと電話があったとき、最初、何かの詐欺かと思いました(笑)。お話を伺って、お役に立てるお手伝いができればな、と思いました」 平澤さんは2016年3月に、母を肺がんで亡くしていた。垣添と出会ったのは、三回忌の法要の少し前のことでもあった。垣添が改めて感謝を述べた。 「私も相当親切なほうだと思いますが、世の中にこんな親切な人がいるとはびっくりしました」 5月には、泌尿器科医なのに尿閉に悩まされた。医師から酒を禁じられた。 「あれがつらかったですねー。居酒屋に入っても気が散らないように定食を頼んで、水を飲みました。あんな生活をしたのは初めてです」 月桂樹の冠をかぶって報告をする垣添。会場の壁面には傑作写真が飾られた。
月桂樹の冠をかぶって報告をする垣添。会場の壁面には傑作写真が飾られた。
若い職員が情熱を感じて感激!
 日本対がん協会群馬県支部の戸塚俊輔専務
理事とのトークショー。
日本対がん協会群馬県支部の戸塚俊輔専務
理事とのトークショー。緑色の稲穂が飛んでくる
次に、テルモ株式会社の中北香子さん、高木則文さん、和地恵さん、小山田香さんが登壇した。 テルモは健康経営が社是で、16カ所で、総勢27人が同行してくれた。緑のTシャツ、サバイバー支援の緑の幟を作成して、垣添の移動に合わせて支店から支店へリレーした。支援を呼びかけたのは、がん医療にかかわる商品を担当している中北さんだった。 「今回の壮大なプランを聞いて、全国の支店長に応援を呼びかけて、みなさん賛同してくれました。京都支店長が3日間ぐらい同行して、『次の週は仕事にならなかった』と言っていました。先生の歩く姿に勇気をいただき、今後も応援したいと思っています」 サバイバーでもある小山田さんは、会社や家族の理解で仕事を続けている。会社の衛生管理室の看護師から、定期健診の度にメールが届き、心が温かくなるという。 「参加するにあたり一番不安だったのは、先生は歩くのが速いということです。ウォークに備えて、会社の行き帰りにも早歩きしていました。でも当日は、先生が優しくゆっくり歩いてくれたのでついていけました」 テルモの会社を挙げての支援は、垣添にとって印象深かった。 「テルモの支店に差しかかると、緑色の稲穂が飛んでくるというのかな、そういう感じで同行する方が現れて一緒に歩いてくださいました。本当にありがたいことです」 報告会に来場されたテルモ株式会社のみなさんと。
報告会に来場されたテルモ株式会社のみなさんと。
Don’t ever give up!
 坂本徹医師。手に持っているのがオリジナ
ルの募金箱。
坂本徹医師。手に持っているのがオリジナ
ルの募金箱。がんになってから百名山を登り始めた
 山形から来られた竹永哲夫さん。懇親会用に
自社のサラミを提供してくれた。
山形から来られた竹永哲夫さん。懇親会用に
自社のサラミを提供してくれた。誰でもなる病気なんだから
日本人の2人に1人が生涯にがんになり、5年生存率が6割を超えた時代。しかし、がんになると、強い疎外感や孤独感、恐怖にさいなまれるという状況を改善したい。「がん=死」のイメージを変えたい。ウォークを始めた背景には、そんな思いがある……。 「がんなんて誰でもなる病気なのよ、と、92歳で胆のうがんの手術をされた瀬戸内寂聴さんが言っています。がんサバイバー支援のため昨年立ち上げたがんサバイバー・クラブの知名度を上げて、ご寄付も増やし、10年先には会員100万人を目指し、サバイバーの声を広く伝える国民運動にしていきたい」 会場には、ウォークを支えてくれた方々のほか、医師仲間、山仲間、飲み仲間、桐朋中高時代の同級生たちの姿があった。 桐朋の同級生のひとり、作家の嵐山光三郎さんは8月下旬、週刊朝日の連載エッセイ「コンセント抜いたか」で、ウォークのことを「カキゾエ黄門漫遊記」と題して2週にわたって取り上げた。垣添を「やると言いだしたらダンコ決行する後期高齢ドクター」と愛着を込めて記した。 助さん格さん不在だったカキゾエ黄門ドクターは後日、 「笑いが多くて楽しい会でした。多様な方が来られていたのに、みなさんがサバイバー支援の方向を向いていることがうれしかった。手ごたえを感じました」 と、この日の報告会を回想した。 垣添がウォークの間背負っていたオレンジ色のバックパック。
垣添がウォークの間背負っていたオレンジ色のバックパック。
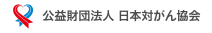


 第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」
第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」 長期休みの不安をどう解消する?
長期休みの不安をどう解消する? 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」