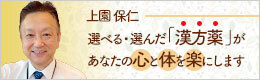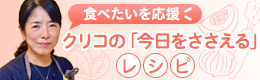日本対がん協会は、「がんアドボケートセミナー2025~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~」を開催しました。このセミナーは、日本のがんを取りまく課題解決に向けて、何らかの取り組みをしたい方(すでに取り組んでいる方)が、がんに関する知識を学び、課題について仲間とともに考え、ご自身の次のアクションにつなげていくことを目指しています。
本セミナーはこれまで、定員約40名の対面講義形式で実施してきましたが、今年は新たに「二部構成」で開催しました。1部の動画学習(入門講座)では、定員を設けず、がんに関する課題解決を志す方が気軽に学べる環境を整備。2部の対面講義(専門講座)では、これまで同様に、参加者同士の対話を通じて課題解決に向けた姿勢を培う少人数制プログラムを行いました。
■1部:動画学習(入門講座)
・開催日程:2025年6月10日~9月30日(112日間)
・開催形式:動画公開(YouTube限定公開)
・申込人数:436名(※2部参加者41名含む。2部参加者も1部受講対象のため)
■2部:対面講義(専門講義)
・開催日程:2025年7月6日(日)10:00-17:00
・開催形式:1日限りの対面開催
・会場:国立がん研究センター 築地キャンパス 研究棟
・申込人数:101名(※定員を超える申込があったため提出課題によって選考)
・参加人数:41名
1.1部:動画学習(入門講座)
1部の動画学習では、がんを取り巻く課題解決に取り組む際に基礎となる知識を気軽に学べる入門講座として、次の7本の動画を用意しました(YouTube限定公開)。
1.「科学的根拠に基づく医療(EBM)とメディカルリテラシー」佐々木 治一郎 先生/北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 教授
2.「患者から『健康食品を使ってみたい』と相談されたら、どう対応すればよいのか?」
大野 智 先生/島根大学医学部附属病院 臨床研究センター 教授
3.「サイコオンコロジー(精神腫瘍学)とは?」
明智 龍男 先生/名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野 教授
4.「緩和ケアと支持医療のこれまでとこれから」
渡邊 清高 先生/帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 教授
5.「医療分野の研究開発における患者・市民参画(PPI)~共に進めていくことの重要性~」
安藤 弥生 先生/国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 臨床研究支援部門研究企画推進部臨床研究支援室/血液腫瘍科
6.「がん患者支援活動をするにあたり心に留め置くとよいこと(個人情報法令順守とバウンダリー)」
平井 理心 先生/筑波大学附属病院 公認心理師・臨床心理士、医療メディエーターS認定(Senior Trainer)、茨城県院内臓器移植コーディネーター、心理士ジェネラル・リスク・マネージャー
7.「患者支援のさまざまな資源 ~がん相談窓口の活用ついて~」
北見 知美/公益財団法人日本対がん協会 相談支援室 マネジャー
科学的な根拠に基づく医療の考え方や、信頼できる情報を見極める力(メディカルリテラシー)を身につけること、そしてがん医療やがん患者さん・ご家族を支える仕組みを幅広く学び、視野を広げることを目指したプログラム構成です。初めて学ぶ方にとっては入門編として、すでに活動している方にとっては知識を整理し最新情報を得る場として活用いただきました。
視聴を終えた参加者を対象に実施したアンケート(回答率27.6%)では、学びの機会への感謝の言葉や、今後の活動に今回学んだことを活かす強い意思を感じられる声が寄せられました。「自分のがん罹患が分かってから、常に支えられる側だったと感じています。それだけに、これまで受けた支援をこれからがんと診断される“次の患者さん”へと申し送りできればと考えています。そんな思いに、知識と熱意が等しく大切なのだと、改めて教えていただきました。」という、参加者の気づきと意識の変化につながった声も届きました。
2.2部:対面講義(専門講座)
2部の対面講義(専門講座)では、主体的な活動をしている方々を中心にご参加いただき、対話を通して課題解決と実践に結びつける基本姿勢を培い、仲間とのネットワークをつくり活動への活力向上につながる時間を目指しました。

野澤桂子先生(目白大学 看護学部 看護学科 教授)は「アピアランスケアを社会課題として考える」と題したテーマで講演をしました。30年近く前、日本では、患者は生きられればそれ以外のことは我慢して当然というのが当たり前の時代に、フランスの医療施設でがん患者さんが最期まで普通に暮らせるよう支援されている姿に衝撃を受けたとのこと。その後、通院治療するがん患者さんが増えたこと、がん医療の進歩によりさまざまな副作用に対応する必要性が出てきたこと、そして何より患者支援に対する社会のコンセンサスが生まれてきたことなどを背景に、アピアランスケア(外見ケア)は日本でも急速に進歩しました。

アピアランスケアとは、医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアのことで、患者さんそれぞれに適した方法で外見の問題に対処し、変化した自己像に折り合いをつけながら安心して社会生活を送れるよう支援することを目的としています。決して美容だけのことではなく、老若男女すべてのがん患者さんの社会的な悩みの解決を含んだ社会課題であることを理解していただきたい、と述べました。苦痛の改善には身体面、心理面、社会面それぞれの側面から解決を目指す必要があるとし、支援者に心がけてほしいポイントについて事例を挙げて具体的に伝えました。
医療の場で外見をサポートするゴールは人と「社会」をつなぐことで、大前提としてあるのは、適切な治療を受ける機会を外見の問題で失わせないようにすること。それを根底に置いて、患者さんが症状に振り回されずに社会とたくましく関わっていけるよう、是非患者さんを支えてほしいと、参加者に語りかけました。

小口浩美さん(一般社団法人LINKOS 共同代表)は、「がん教育を当事者視点で考える」と題して、がん教育の現状と課題についてお話ししました。がん教育とは、学習指導要領に記載されている健康教育の一環であり、学校で行われる自他の健康と命の大切さを学ぶ授業のこと。学校にはおよそ140の教育テーマがあり、その中の一つに位置づけられています。小口さんは、他の教育テーマとも融合させて、経験したからこそ伝えられる大切なメッセージを届けていきたいと考えているとのことでした。そのためには、単に経験を語るのではなく、「何を伝えたいのか」「何を知ってもらいたいのか」という明確なメッセージを意識することが重要だと強調しました。最後に、「誰のためのがん教育か」という原点を忘れずに、これからも種をまき、芽を育てていく思いで取り組んでいきたいと語りました。

大井賢一さん(認定NPO法人がんサポートコミュニティー 事務局長)は、「がん患者や市民の声を聴き、意見を尊重するアドボカシー ~身近にできる支援を考える~」をテーマに講演しました。大井さんは、アドボカシーとは「権利を擁護する」という意味であり、「誰かの声を拾い上げて社会に届けること」と考えて欲しいと、参加者に伝えました。アドボカシーには、「自己を守る私益性」、「ある個人を支える共益性」、「制度を擁護する公益性」の3つの側面があると説明し、大井さんの団体の活動が、目の前の患者さんに寄り添う支援(共益性)から出発し、現在は制度設計(公益性)にも関わるようになってきた経緯を、支援団体としての具体的な取り組みの一例として紹介。

また、ピアサポートを行う際に留意すべき点として、「支援する側が相手の課題に巻き込まれる可能性があること」、「真摯に向き合う姿勢が大切であること」、「支援する側こそ多くの支えを得ているという視点を忘れないこと」の3点を挙げました。さらに、「支援者として自分自身が達成感を得る中でも、支援される相手が本当に満たされているかを常に意識してほしい」と呼びかけ、特に情報提供の場面においては「自分の立場としてできること・できないことを意識して対応することが大切」と、参加者に注意を促しました。
セミナー最後は、「仲間とともに行動を広げるために ~ワークショップ(ストーリー・オブ・セルフ)~」とのテーマで、特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの木山侑香さん、松澤桂子さんが進行役を務めたワークショップを実施しました。

課題解決に向けて仲間とともに取り組むためには、どのようにリーダーシップを発揮したらいいのかー。今回のワークショップでは、それぞれが持つ能力や資源を活かし合い、雪の結晶のように広がっていく「スノーフレーク・リーダーシップ」の考え方を学びました。参加者は、自身の経験や価値観を語る「ストーリー・オブ・セルフ」に取り組み、自分の原点や困難、そこから生まれた思いを言葉にしました。語ることで仲間に思いを伝え、希望や勇気を分かち合うとともに、自分自身の内にある力に気づく、という一連の体験をしました。終了後には「想像していなかった自分の価値を、人からのフィードバックで知ることができた」といった声も寄せられ、参加者同士のつながりや新たな一歩への手応えが感じられるひとときとなりました。

終了後に実施したアンケート(回答率80.5%)では、参加者の多くから前向きな反応が寄せられました。「あなたが取り組みたい(または取り組んでいる)ことに“活かせる学び”はありましたか?」との問いに対しては、「おおいにあった」「ある程度あった」との回答が100%を占めました。また、取り組みへの意欲や視野の広がりを問う質問に対しても、9割を超える肯定的な回答が得られました。これらの結果から、2部参加者の意識の変化や次のアクションにつながる機会となったことがうかがえました。
3.まとめ・今後
1部・2部いずれのアンケート結果からも、本セミナーが、参加者の比較的短期間でのポジティブな意識・行動の変化や、活動の質の向上に寄与できた可能性が示唆されました。1部動画学習では、「がん患者支援に携わるうえで必要な知識をわかりやすく学べる機会」として一定の成果が見られ、2部対面講義では、「参加者同士が活動や課題意識を共有し次の一歩を考える場」として、交流促進にもつながる有意義な時間となり、それぞれの部で掲げた「到達目標」に沿った意識・行動の変化が確認されました。
今回新たに導入した1部動画学習と2部対面講義を組み合わせた2部構成の開催形式には、400名を越えるお申し込みをいただき、アンケート結果も概ね好評を得ることができました。一方で、1部動画学習では、申込をしたが視聴に至らなかった参加者も一定数おり、原因の把握や対策が今後の課題となりました。
本セミナーが、全国でがん患者支援活動に取り組む皆さまにとって有益な学びや出会いの機会となり、日々の活動の力につながりましたら幸いです。今後も、がんになっても希望とともに生きることができる社会の実現をめざし、課題解決に取り組む方々を応援し、支援の輪をさらに広げてまいります。

*当日の撮影協力:木口マリ さん(フォトグラファー、がんフォト*がんストーリー代表)
一般社団法人オンコロジー教育推進プロジェクトが「Oncology Dream Team Project(がん医療への夢を語り、共有し、実現させるための患者・家族・一般生活者による参加型プロジェクト)」の一環として、2010年より展開してきた「ドリームキャッチャー養成講座」を原点としています。
日本対がん協会が共催に加わり、上野直人先生(ハワイ大学がんセンター センター長)ご協力のもと、次世代のアドボケーター育成を目指して開催してきました。現在は日本対がん協会が主催としてその想いを受け継ぎ、より多くの方に学びとつながりの機会を届けるよう、発展を続けています。
これまでの参加者はさまざまな分野で活躍しており、がんに関わる社会の担い手として、それぞれの立場から活動を広げています。
2024年 開催報告 、2023年 開催報告 、2022年 開催報告 、2021年 開催報告 、2019年 開催報告 、2018年 開催報告 、2017年 開催報告
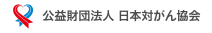


 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内
「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 長期休みの不安をどう解消する?
長期休みの不安をどう解消する? 第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」
第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」 クリコの「今日をささえる」レシピ/第10回 春菊のポタージュ
クリコの「今日をささえる」レシピ/第10回 春菊のポタージュ